取組紹介一覧へ戻る
コミュニケーションを密に働き続けたい会社へ進化
株式会社大智鍛造所
| 所在地 | 川西市加茂6-45-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 自動車、農機、建機の部品製造 |
| 従業員数 | 48人(男性44人、女性4人) |
| 冊子掲載 | 令和2年度WLBな会社ガイド |
| 冊子PDF | 詳細をみる |
| 公開日 | 2021年2月19日 |
※上記については、表彰時あるいは情報誌等記載時のデータです。
「社員の幸せを支援すること」を目的に、ワーク・ライフ・バランス(WLB)の実現に取り組む大智鍛造所。中でも、2工場で生じていた情報格差を埋める「バディ制度」は社員間のコミュニケーションを向上させ、不良率の削減にもつながっています。

意識調査で課題をあぶり出す
鉄の丸棒を1250度まで熱して軟らかくし、ハンマ式鍛造機で打撃を加えて金型成形する熱間ハンマ鍛造を得意としています。強靭で折れにくい部品の製造に適した加工法であることから、同社の製品の多くは、安全性が求められるブレーキやステアリング等の自動車部品に使われています。
社員が安心して働き続けられる会社づくりに早くから取り組み、半日単位の有給休暇制度を設けているほか、社員の親睦旅行、部活動を実施するなど、さまざまな方策を進めてきました。「これまで取り組んできたことについて社員がどのように感じているのかを確かめ、さらなる改善につなげたい」との思いから、2017年、職場環境などに対する意識調査を実施。その結果、課題として挙がったのが「コミュニケーションの向上」でした。
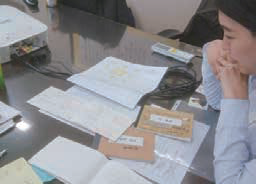
教育と情報共有を兼ねたバディ制度
同社には本社工場と、そこから車で5分ほど走った場所に立つ久代工場があります。コミュニケーションの向上を求める声は、特に久代工場の社員から多く出ました。「久代工場は製造工程のうち後半の検査、出荷を担っています。不良品を出さないようにチェックする仕事は苦労を伴いますが、できて当たり前と思われがちです。また本社からの情報が滞ることがあり、そのために出荷が遅れ、残業時間が長くなるなどの弊害が出ていました」と代表取締役社長の大智靖志さんはその理由を分析します。
これを解決すべく3年前から始めたのが「バディ制度」です。バディとは2人組のこと。本社工場で製造を担当している社員とその上司である課長・主任が2人組になって、久代工場の検査、品質管理担当者にヒアリングを実施。その対策をバディの2人で改善に結び付けるという仕組みです。バディは7ラインある製造機械ごとに結成。何が不良として出やすいのか検査、品質管理担当者から指摘を受け、それを踏まえて工程やチェック方法の見直しを行いました。
一方、検査、品質管理担当者は、不良が生じる要因について製造担当者から説明を受けることで不良の特性が理解できたといいます。「ヒアリングや議論の場は社員教育の場にもなっています。両工場の意思疎通がスムーズになり、検査や出荷の見通しも立てやすくなりました」と大智社長。検査の繁忙期には、製造や事務担当部門からサポートに入るようにもなったそうです。
結果、平均不良率は2017年度の1.35%から19年度は0.8%に改善。情報共有による作業の円滑化なども手伝って、1人当たりの月平均残業時間は17年度の23.7時間から19年度には9.8時間に大きく減少しました。

働き続けたいと思えるように
意識調査の中で希望が多かった「有給休暇の充実」についても2017年にすぐ対応。本人の結婚の際は5日、妻の出産時には2日など、特別有給休暇を新たに設けました。有給休暇を活用して旅行した社員の様子を「社員の旅行通信」としてSNSで共有し、取得を促す工夫も行っています。
新入社員には1年間毎日、作業日報の中で不安や仕事に対する疑問を伝えてもらい、アドバイスを返しています。この経験を外国人技能実習生にも応用し、来日してから1年間は、総務部の岩木理絵さんが毎日一人一人と交換ノートをやりとり。「以前は不満がかなりたまってから外国人全員でぶつけてくることがありましたが、小さなうちに芽を摘むことで、それもなくなりました。皆、仕事に集中して頑張っています」と岩木さんは話します。
WLBの目的を「社員の幸せを支援すること」と語る大智社長。現在はIoTを導入し、機械の稼働・停止時間や各部品の製造進捗状況を自動的に把握して全員で共有。さらなる生産性向上に取り組んでいます。

取組を検索する
下記の項目をチェックして「検索する」ボタンをクリックしてください。

